
大腸

大腸
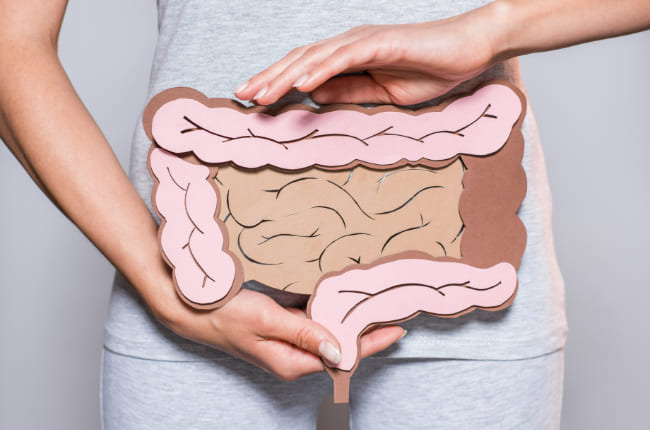
便秘が続くと、お腹の張りや不快感、体のだるさなど、日常生活に影響を与えることがあります。
「たかが便秘」と放置しがちですが、慢性的な便秘の裏には病気が隠れていることもあるため注意が必要です。
便秘がちになるには、複数の要因が複雑に絡み合っているケースが多くみられます。もっとも一般的な原因は、食事の偏りや水分摂取の少なさ、運動不足といった生活習慣の乱れによるものです。加えてストレスや睡眠不足などによる自律神経の乱れも、腸の働きを低下させ、慢性便秘症につながる大きな要因の一つです。
腸管内の通過が物理的に妨げられる腸閉塞(イレウス)、便の通過が困難になる大腸がんなど消化器の病気が隠れていることもあります。これらの疾患は早期発見が重要です。明らかな臓器の異常がないものの、便秘や下痢を繰り返す過敏性腸症候群(IBS)の可能性も考えられます。さらに年齢や性別も便秘に関係しており、女性はホルモンバランスの変化によって腸の動きが影響を受けやすく、高齢者では腸のぜん動運動が低下するため便秘が起こりやすいです。また、頻尿の薬や抗うつ薬、鉄剤など薬の副作用として便秘が現れることも珍しくありません。糖尿病や甲状腺機能低下症、パーキンソン病などの病気によって腸の動きが抑制されている場合もあります。
便秘の背景には生活習慣だけでなく、さまざまな病気が関与している可能性があるため「いつものこと」と軽視せず、症状が続く場合は一度、消化器内科での診察をご検討ください。
便秘は排便の回数が減るだけでなく、硬くてコロコロとした便しか出ない、排便時に強くいきまないと出ない、排便後もすっきりしない(残便感)といった症状が出ることもあります。また、さまざまな体調の変化を引き起こすこともあります。腸内に便やガスが滞ることでお腹が張る、吐き気や食欲不振を伴うといった全身症状、さらに便秘が続くと倦怠感や集中力の低下、睡眠不足など日常生活に影響する体調不良を引き起こすことも少なくありません。このような症状が慢性的に続く場合には、単なる生活習慣の乱れではなく、何らかの病気がかくれている可能性もあるため注意が必要です。
腸閉塞(イレウス)
腸管が詰まり、便などの内容物が先に進まなくなる状態です。主に術後の癒着やがん、硬い便、結石などが原因です。腹痛や吐き気、嘔吐、血便などもみられます。便やガスが出ない状態が続くときは緊急対応が必要です。
大腸の内壁に発生する悪性腫瘍で、特に50代以降で発症が増加します。早期は無症状のことが多く、進行に伴い便秘や下痢を繰り返す、血便、便が細くなる、腹痛、貧血などが現れます。
検査によって異常は見つからないにもかかわらず、腹痛や便秘、下痢などの便通異常が慢性的に続く病気です。比較的若い方や女性に多く、ストレスや食生活の乱れ、腸内環境の変化などが関係していると言われています。便秘が主症状の便秘型、下痢が主症状である下痢型、どちらもみられる混合型があります。
下痢が続くと腹痛や脱水などを引き起こし、生活に支障をきたすことがあります。食あたりや風邪による一時的な下痢もあれば、数週間以上続く慢性的な下痢の中には、重大な病気が隠れている可能性も考えられます。
下痢が続く原因には、食事内容や生活習慣、一時的な感染症から消化管の病気まで、さまざまな要素が関係しています。一般的なのは、ウイルスや細菌による感染性胃腸炎です。特に冬場に流行するノロウイルスなどは、下痢だけでなく嘔吐や発熱を伴うため、脱水や体力低下に注意が必要です。
また脂っこい食事やストレス、アルコールも下痢を起こす原因になります。一方で、何週間も下痢が続く場合には、潰瘍性大腸炎やクローン病といった炎症性腸疾患、大腸がんなど、重大な病気が関係している可能性があります。
さらに過敏性腸症候群(IBS)のように、検査では異常が見つからなくても、ストレスや自律神経の乱れが原因で下痢を繰り返すケースも少なくありません。検査で異常がなく、原因を特定できない場合は、機能性下痢症と診断されることもあります。
他には、糖尿病や甲状腺機能の異常、薬の副作用など消化管以外の病気も、下痢を引き起こすことがあります。下痢が続いているときは、自己判断せず、消化器内科を受診してください。
下痢は便が通常よりも水っぽくなり、排便回数が増える状態で1日に3回以上の軟便や水様便が続きます。4週間以上持続または反復する下痢によって、日常生活に様々な支障をきたしている場合は慢性下痢症と診断されます。
高齢者や小さな子どもは、繰り返す下痢によって脱水や電解質異常などを引き起こす可能性があるため、症状が続く場合は注意が必要です。
下痢に加えて発熱や腹痛、血便、体重減少がある場合は、感染症や炎症性疾患の可能性があり、早急な対応が必要です。
大腸粘膜に発生します。早期は無症状ですが、進行すると血便や下痢・便秘の繰り返し、体重減少がみられます。特に50歳以上では注意が必要です。
大腸の粘膜にびらんや潰瘍を生じる慢性の炎症性腸疾患です。下痢以外にも粘血便や腹痛、発熱などが繰り返し起こります。若年層に多く、長期的にはがん化のリスクがあります。
潰瘍性大腸炎と同じ、炎症性腸疾患です。口から肛門まで消化管全体に炎症を引き起こす病気で、10代後半から20代に多く発症します。下痢だけでなく発熱や体重減少、肛門病変などが特徴です。
主に中高年女性にみられます。大腸の血流不足により粘膜が障害され、腹痛や水様性下痢、下血がありますが、数日から1週間程度で自然に軽快することが多いです。
検査で臓器の異常が見つからないにも関わらず下痢が続く場合、過敏性腸症候群(IBS)や機能性下痢症と診断されることがあります。過敏性腸症候群(IBS)は症状の出方によって下痢型・便秘型・混合型と分類されます。機能性下痢症は、原因の特定ができず、慢性的な下痢が4週間以上続く状態です。
トイレで排便後に赤い血が混ざっていたり拭いたトイレットペーパーに血がついていたりすると、不安になる方も多いのではないでしょうか。
血便の原因は痔などの良性疾患から、炎症性腸疾患や大腸がんなどの重大な病気までさまざまです。見た目の色や出血の量だけでは原因を判断するのは難しく、放置すると症状が進行することもあります。
排便時に以下のような症状を伴っている場合は、消化管の病気が隠れている可能性があります。
血便が出る原因は、消化管のどこかで出血が起こっていることにあります。出血しているところが肛門に近いほど、血液は鮮やかな赤色として便に現れやすく、逆に上部の消化管からの出血では黒っぽく変色しやすくなります。
代表的な原因は肛門周辺からの出血で「痔核(いぼ痔)」や「裂肛(切れ痔)」です。
また、腸の内部で炎症や潰瘍が起きると、便と混ざる形で血便が現れます。たとえば細菌やウイルスによる感染性腸炎では、腸粘膜が傷つき、下痢や腹痛とともに出血が起こります。
炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)は、腸の慢性的な炎症により粘液や血液を含む便が続く病気です。
大腸がんや大腸ポリープでは、腫瘍やポリープが大腸内を塞いでしまうと、便が通過するときに擦れて出血が起きるケースもあります。便に血が混じり、便も細くなるといった変化があるときは、早めに検査を受けましょう。
血便とは、便に血液が混ざっていたり、排便時に鮮血が出たりする状態を指しますが、出血している部位や原因によって、血の色や出方が異なります。
肛門付近の出血であれば、鮮やかな赤い血が便の表面やトイレットペーパーに付着することが多く、痔核(いぼ痔)や裂肛(切れ痔)などが疑われます。
一方で、腸の内部からの出血では、便に血液が混ざったり、粘液や膿を伴う血便が見られたりすることが一般的です。炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病)では、このような症状が慢性的に続く傾向があり、下痢や腹痛、発熱などを伴うこともあります。
感染性腸炎や虚血性大腸炎では、突然の下痢や腹痛に加え、血便が現れるケースがあります。腸管出血性大腸菌(O157)などでは、激しい腹痛と血性の下痢が特徴です。
血便の症状は軽く見えたとしても、出血の量や頻度、色の違いによっては深刻な病気が隠れていることもあります。便の異変が気になる場合は、早めに消化器内科を受診しましょう。
裂肛(切れ痔)
硬い便や便秘のあとなどに起こりやすく、排便時の強い痛みと少量の鮮血を伴います。
感染性腸炎
細菌やウイルス感染によって腸に炎症が起こり、下痢や発熱、腹痛とともに血便が出ることがあります。感染時に血便がみられる細菌は、カンピロバクターや腸管出血性大腸菌(O157)、サルモネラ菌などが代表的です。
大腸の血流障害により、突然の腹痛とともに血便が現れます。中高年の女性に多くみられます。
top